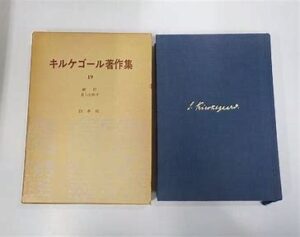キルケゴール著作集18。
「私の全著作活動の思想全体は、いかにしてキリスト者となるか、という一事につきることを常に念頭においていただくよう、好意ある読者に切に私は最後のお願いをする。」
── そうか、そうだったのか! と納得した。
「あれか、これか」が、このひとの基底にあること、常に「あれか、これか」を感得せざるを得ない(「瞬間」も、他の著作を読んでいてよく文中に目にする、さりげなく書かれている重いキーワードだが)流れ、このひとの川をつくる源流──
「ほんとうのキリスト者にきみはなろうとするのか、しないのか」もこの「あれか、これか」にふくまれる、読者および世界への問題提起、と思うのは軽薄だろう。
だがあるていど軽薄に読んで、いいんじゃないかと思えるようになった。軽薄というより、よくわからないところは読み流してもいいんじゃないか、と。
キルケゴールの言葉の使い方はかなり独特だ、ふだんこちらが発想したことのない意味を、ひとつの語句にふくませる。たとえば「自分に嫉妬する」。「自分に嫉妬する」、この言葉から続く文章はよくわからない。嫉妬とは自分以外のものにするものだと、自分としてはずっと捉えていたからだ。しかし、確かに嫉妬というのは自分に対してしているのかもしれない。
「自分に嘘をつく」ことがわかる以上、同じように「自分に嫉妬」は大いにあり得ることである。
神は自分を映し出す曇りなき鏡、とするキルケゴールとしては、と考えると、簡単に説明できる気にもなる。でもここで今それを書こうと思わないし、この部分をわからないとして読み流した以上、書くこと自体が軽薄になる。
「愛のわざ」も読んで(「終えた」とは言えない)、やはり巻末の訳者解説は的を得ている。それを引用すれば、この本が、キルケゴールが、読者によく伝わるだろう気も強くする、この今自分が書くにあたって。でも、それではつまらない。
何冊目だっけ、この著作集を読み始めて… 今自分が感じるのは、今自分が感じていることで、これが最も強く感じられることで、「荘子、ブッダ(たぶんソクラテスも)、ひょっとしたらニーチェ、かれらの言わんとしたことをキルケゴールのいうほんとうのキリスト教は言っている」ということ。
これは荘子のこれに呼応する、これはブッダの、これはニーチェの、と、その一字一句を挙げることもできる。言いたいことが、彼らと同じだ、と思える言葉がキルケゴールにある。
それも、しかし小さなことに思える。それは自分の中で大きなものになっている。ああ!と確信する、彼らは同じことを言っていた、と。
しかし今読んでいるのはどこまでもキルケゴールで、彼らではない。これは自分の中の大きな確信、沢山の著作をした(大きな、ともいえる)キルケゴールにとっては小さなことだ。自分が今まで読んで感銘された言葉をここにも見ただけで、かれにとってはほんの一部、自分にとっては大きなことになっているにすぎない。
かれの書き方は、常に「一つ」ではない。必ず「二つ」だ。一つのことを言いたいのだろうが、そのためには一つのことだけでは言いたいことも言えない── 弁証法って、こういう仕方?
いや、どんな書き方、表現方法を用いようが、かれの言いたかったことは「真のキリスト者になるために」だったことは、この18巻の出だしを見て「わかった」といえる。
実は、今まで読み進めていて、随分悲しくなった。胸に来て、読むのがつらかった時も少なくなかった。そのたびに、読むのをやめた。でもまた読み始めた、この反復のうちで、何が悲しいって、結局ブッダやソクラテスを読んで感じたこと、「この現代世界はキルケゴールが訴えていた、それが正しいとするならばの話だが、正しいことと、なんと真逆に、また全く彼の訴えが残っていないかのように世界が、現代社会が、営まれていることだろう」ということだ。
いや、たぶん、きっと、正しいのだ。ブッダもキリストも、正しいこと、真のことを言っていたのだ。荘子もソクラテスも、ほんとうのことを言っていたのだ。
正しい人間の生き方を。まことの、人間のあり方を。ほんとうの人間の生き方を。
それがなぜ、なぜこんなに、というところに、自分は悲惨な、やはり悲しい、としか言えないが、絶望的な、ひどい気持ちになるということだった。
だが、そしてキルケゴールは言うのだ、「絶望の中に希望がある」と!