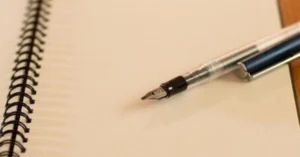いつも愛用、愛用としか言い難い某投稿小説サイトがサーバーダウン?か何かしたのか、入れなくなってしまった。
そっちとこっち(note)に投稿しているのだが! そっちから、「書くことについて」書いたことが沢山あるので、持って来ようとしたのだが、断念。ほんとに脆いよな、このネット環境ってやつは。電波がなくなりゃ消える… 人との関係も、いっぱい書いた文章も。
書くことについて… 自分のために書く、が基本で、ということ。
友達が、ちょっと身体的、精神的か、とにかくハンディのある子どもちゃんをもっているのだが、奥さんもお身体が弱く… だがそんなことは彼にとってパワーの源になっている… そんな友達がいる。
彼は、「ぜんぶ、まるごと」受け容れる、自分のものとする、受け止めて自分のものとする、そんな器をもっている。
だからまわりから「シアワセじゃなさそう」(よけいな節介だ)と見られたとしても、彼は、少しはその意見を意に介すだろうが、さして気に留めない… ように見える。実際、そうだと思う。
なかなか彼のような人はいないと思う、少なくとも自分の知る限り彼だけだ、酒を飲んだりくっちゃべったり仲良くなれた人の中で。
絵を描き… ぼくも家人も何枚も買った… そう、絵、原画というのはこの世でほんとうに唯一つだ、人の存在のような存在だ。
── 文章といえば、ここで投稿し他のサイトにも投稿でき、さしあたって1つに限らない。原稿だろうがワープロだろうが、内容は同じだ。同時にいくつもの場所で1つのものが目にすることができる。ああ、絵ってやつは本当に!
そう、こないだ「モーゼスおばあさん」の絵を「世界名画の旅」(朝日新聞社)で見た、その解説も。
あの絵は「実際には今存在しない風景」なのだそうだ。モーゼスおばあさんの想い出、過去の風景… 現に存在しないものを彼女は絵に描いた!
そしてその絵は存在し、こないだ行った東京の実家にも飾ってあった、もちろん原画ではないが! 日本でもどっかの企業が何点か買い、美術館で鑑賞できるそうだ。
〈素朴派〉。モーゼスおばあさんも絵を習ったことはなく、70歳をすぎて初めて描き始めたそうだ、誰に習うこともなく。
そういう描き方をした人は絵画の世界では〈素朴派〉と呼ばれるらしい。
埼玉の東松山にある丸木美術館にも、今はどうか知らないが丸木スマさんの絵が展示されていた。あの絵はよかった、ほんとうに素朴で、金魚だか猫だかニワトリだかが、まるで子どもが書いた絵のように、でもしっかり、温かさがこっちに伝わってくるような絵だった。まさに素朴、純心、きれいな心、やさしさ、いろんなものが、とても善的なものが、善なんて意識しようがしまいが構わず、こちらに感じさせてくれる絵だった。
絵、音楽、本、それらは受動するものだが、書くことは能動で… だが書かれたものは、それによって受動される。
なんなら書いている時点で言語化されることで書いている本人も受動する。主体と客体、能動と受動、つまりはこの両者の媒体、繋ぎ目として作品、文章、形がある。
書いている能動・主体としては、この思い、気持ち、書こうとする漠とした、本人にしか持ち得ないものが、形になる、有象化する、象形化する。
どんなにこの文字が人からどう見られようが、その「人」も自分でつくっている、自己の内部のものだ。人の目は自分がつくっている。そして実際の人は、自分が思うほどこちらに注意を向けていないものだ。自意識過剰は現代の病!
ということを認めて、つまり受け容れて、自分でつくる客観も、まわりが実際にこちらを見る目も、まるごとぜんぶ受け止めて… それはぜんぶ自分のためであり、自己があるためであり、けっしてその根源に「ほんとうの他者」はいないということ、畢竟自己の内へ内へ、内面性に向かう、そこから始める── どうしたって自己へ向かうことになる、書いている段階、形にする段階では。
それを最初から客観ばかりを重視して、その客観する自己(ウケ狙い!)をする自己への意識より、表象される文字ばかり、どう見られるかばかりを意識しては、まったく誰が書いているか分かったものでない。
この意識、この意識が1mmでもあるかどうかで、全く形も変わってくる… パッと見て、あ、この人は!と分かる。漏れるんだ、どうしても、その人の「意識」は。
自分がヒビ割れ、漏れたものは、もうあとは実在するそれを見る、それに接する人に、もうどうとでも解釈され、好きなようにコネ回される。
そう、こちらが自由であるのは、書いてる本人が自由であることができるのは、書いてるその最中でしかない。
それなのに、ハナからその自由に客観の足枷を自ら嵌め込み(ウケ狙い!)、自己を喪失しながら歩みを進める、喪失していることにすら気づかない、無自覚の境地で無神経であり続けるが如くの人が少なくなく見受けられる、… いいんだ、何だって!
ただこっちはもうそういう書き方をしたくない、それだけの話だ、わかる人にわかり、わからん人にはわからん… 日常生活でも同じこと、そして人は変わる、何かの弾みに、ヒョンなことから、あっけなく、ジジジと変わる。
書くことについての話だった… 自分にとって書くこと、とは?
自分に正直になること、これを第一義にしている、日常生活でも変わらない、自分に嘘はつかない、つきたくない、だから人にもそう接している。自己を欺くことは他者も欺くことになる、二重の欺き、欺瞞は二重苦になる、三重苦にも四重苦にもなる、そんなふうにはなりたくない、まっぴらご免だ…
話を戻す、要するにこうして生きてる(出たゾ「生きてる」)、そのまま書いてる、ただし書く時はひとりの世界で、まっさらなひとりの世界で、飛んでいる… 落ちているのかしれないが、そんな〈客体〉よりも!
内へ内へ、もっと内へ向かって。外よりもよっぽど無限な、井戸、深淵っぽい中、内面性とやらに向かい、向かい、そうして書きたいということだ。
外よりも、こっちの方が… 何しろひとりなのだから!