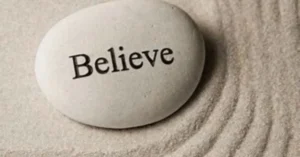しかしつくづく不思議だ、なぜ「仏教」と一括りにされてしまうのか。
日本で最も多いのが浄土真宗、次に浄土宗という。だが、これは親鸞が、法然が始めた浄土真宗であり浄土宗なのだ。
というのも、仏教の開祖といわれるブッダの仏教には「こうしなさい、ああしなさい」という「きまり」がない。念仏を唱えろと言っていないし、お経を詠めとも言っていない。規則、強制がないから宗教として成り立ち得ないのだ。
それなのに「仏教」。まるで中身、内容が違うのに、一括りにされる。
自分としてはお墓参りは東京に行けば必ずするし、お寺のもつ独特の雰囲気も嫌いでない。でもお坊さんという職業には、ちょっと眉をひそめてしまう。いつかハローワークにもあったらしい、「住職募集」。お坊さんというのは、あまり信じられない。
お葬式や儀式的なものは、あくまで生者のためであって、死者のためではない。こちらの気持ちにフンギリをつけるため、現実を受け入れるためにあるんだろうと思う。その式の場で、いろんな人との交流もある。そういう場でしか交流のない交流もある。
こないだ実家に行った時、兄から聞いた話によれば、昔はお坊さんは酔っ払って家に来たそうだ。お彼岸やお盆の時期、毎年お坊さんが家に来て仏壇に向かってお経をあげる(家は浄土宗)。それが終わると、祖母が必ずお酒を出すのだ。各家庭を、家庭訪問する教師のように行く僧侶は、その家その家で一仕事終えた後、必ず酒を飲む(飲まされる?)風習だったらしい。
赤い顔して、酔っ払って持参した木魚を叩き、聞いているこちらにはわけのわからないお経を詠む── なんだか、いいなぁと思った。
その頃(60年位前?)のならわしだったとはいえ、お坊さんは飲酒運転も許されたのかな。でも寛容で、想像するにいい時代だったように思える。
宗教と人間、… 宗教はとかく戦争につながる… あんまりキッチリしなくていいんじゃないかと思う。適当な感じで、そんなムキになることもなく、いい加減な湯舟に浸かるようなふうで。
信じる、信仰心というものに本気ですがり、それをほんとうに信じ込んでいる真面目な人は、ちょっと怖い。