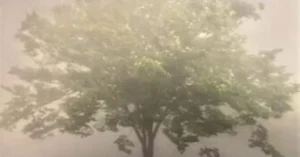キルケゴールを苦しみながら読んでいると、そのまにまにどうしたところで「神」が登場する。キリスト教圏内で育つ者、彼はデンマークだったが、学校の教科に「キリスト教」があるというし、そこに生まれたらもう切っても切れぬ縁のごときものとして、切り離せないものなのだろうと思う。
彼は言う、… ほんとうのキリスト者であることは苦しみ以外のなにものでもない。これがイヤなら、さっさとキリスト教など捨てるがよい! と。
自分は何でもないただの日本人だが、この言葉にはしばし打ちひしがれた。
「自分からすすんで苦しんでいる」自覚があって、さらに「こういう自分なのだ」とわかっている。この自分に向けられた言葉のように感じられたからだ。
さらに「キリスト教など捨ててしまえ」と云ったキルケゴールの気持ちを想った。やっぱり勇気のある人だ。そうせざるを得ない自己を抱えていたとはいえ。
そう、何も苦しむ必要などないのだ、それでも必要とする── いや苦しむ、これがどこまでほんとうか、ということだ。ほんとうは、苦しんでいない、「苦しくない」わけでないから、言葉にすれば苦しい、といっているだけのような気がする。そう、べつに、特に、何も言わなくても、その前に何か感じなくても、感じたとしてもそれはそれだけのことで、それでどうということもないはずなのだ。
自分があるということは、「自」と「分」けた「他」が存在する。頭の中であれ、目に見えるものであれ、それは存在するのだ。それに対する、ということ。そこに発生するのだ、あらゆる感情、心情が。
その対象に、まるごとぶつかる── 向かう。と、なかなかにしんどい。ハネ返されるにしろ受け入れられるにせよ、いわば「一対一」の勝負のような、のっぴきならない何かがそこに萌芽する気もする。
その対象、人であれ物であれ、ある物事であれ、それと自分が対する時(対すると思う時)、それと自分との間の、左斜め空中辺りにもう一つの存在、「神」がいるとしよう。
いや、いるのだ、と思ってみよう。すると、一対一のタイマン勝負、全身(心)で相手、対象に向かう、というより、そんな張り詰めたものでなくなり、何か余裕のようなものが、自分自身の中にもぽっかり生ずる気がする。
相手の言うことをぜんぶ受け止めようとか、こちらの言いたいことをぜんぶ分かってもらおうとか、そんなこだわりが薄くなる気がする。だってそれは中間にいる、左斜め上にいる「神」が断じることなのだから。裁く、というほど大袈裟にはしたくない。
何でも自分で引き受ける、引き受けようとすることは、無理である。
といって、責任を放棄する意味でなく、自分のしたこと、言ったことのオトシマエは自分で負うべきである。
といって、何もそれは「ぜんぶ」ではない。ぜんぶは、自分自身の存在、まるで命、このものをぜんぶ賭けるかのようになる… これまた、無理である。
そのような対象は、この世のどこにも存在しないのだ。
あるとすれば、れいの「神」である。神は自分自身の内に在するとも言われるが、それは換言すれば「ほんとう」というもの、ほんとうのこと、真実、と呼ばれるものである。(ああ、だから真実は一つでない… 100人いれば100通りのそれがある!)
そこで、他者と自己との間にある神と、「私」の中の神と、対座する相手の神、三つの神があることになる。
相手も、自分の内にある神を信じ、こちらも自分の内にある神を信じている。何しろそれがほんとうのことであるからだ。それでは、ああまた戦争だ、そこで仲介役のような存在、それが「中間にいる神」としたい。
まともにぶつかる、ぶつかり合うのは、合おうとするのは、人間の限界を超えた所作のように思う。
これが最善だ、これが!と、決められる由もない。決めるが、それはその時の最善であって、その時を超えて最善であり続けるものはこの世にない、この世にはあり得ないものだ。
その限りにおいて、自分としての最善、近くに行く。最善そのものではない。最たるものは、考えられる最たるもの以上に最たるものとして、左斜め上にあるものである。
と、してしまおう。実際、万物も、その一つである人間も、その発祥を辿れば「無」なのだ。無とは、計り知れないものである。知れないものによってつくられたのが物であり、人間も肉体の限りにおいて物以上にはなれない。
つくられた存在として、つくったものがおそらくあるのだろうと思う。その存在は、あるのだろうと思う。したがって、判断… 背負いこむこと、抱えきれないものを抱えようとすること、これをする・しないの判断、は自分の限界内でしかできず、またそれで全くいいのだ。あとは、かの神に任せよう。
そう考えると、なんだか、気楽になった。