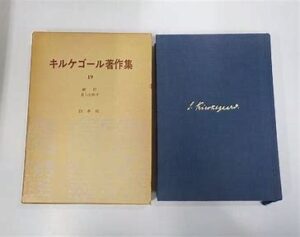キルケゴール「愛のわざ」の下巻を読み始め、つらいのは── ブッダの本を読んでいる時も感じたが、「世の中が、彼の訴えることと真逆の方向に行ってしまっている」ことだ。
ソクラテス(プラトン)を読んでいた時も、全く同様の、つらさを味わった。
ましてキルケゴールは、まさに生命をかけて、それが彼の気質だったとしても、キリスト教圏内の国で、あれほどのキリスト教会批判をする本を上梓したのだ。しかも牧師たち、一般市民が日曜日に敬虔な気持ちで足を運ぶ教会の、そこで説教をする牧師たちのことを。
「ほんとうのキリスト教は、それではない。こうであるのだ、なぜならこうでこうで、こうであるからだ」と、聖書からの言葉を用い、素人の私でも解るように説明している。
「キリスト教の修練」でも、この「愛のわざ」でも。
その姿は、あまりに痛切だ。いわば弱者である者が、「ほんとうのキリスト教」を訴えるために「世界」に向かっている… われわれが、どうしたら「ほんとうのキリスト者」になれるのか、滔々と、情熱をもって(あさはかな情熱や夢ではない)書き続けている。
かれの云う「ほんとうのキリスト教」「ほんとうのキリスト者」を、「ほんとうの社会」「ほんとうの人間」と置き換えて読んでいる自分にとって、その訴えは胸にまさに刺さる思い、…読んでいて、ほんとうにつらくなる。またセリーヌの「リゴドン」も、「年代記者」を自称するセリーヌの戦時下の体験、今映像で見られるウクライナの破壊された町をまざまざと文章の中に見るようで、読んでいてやはりつらくなる。セリーヌはそれでもユーモアをもって、愛をもってと言っていい、あの凄惨な戦争下の人々のこと、自身の体験を書いているが、キルケゴールは真剣そのものに教会批判を書き続けている。もちろんユーモアと愛もある、ただ自分にはそれ以上に痛みを感じる。
しかし「愛」について、これほどこの主題を追って書く、聖書の言葉からその思索、思索どころか彼自身の生きざま、こうやって生きるという、生そのものが書かれている、ここに自分は打たれて仕方ない。言ってしまえば、涙、涙である、心の中はざあざあ雨、顔にある目はこう書いていても涙ぐむ、それほど「入って来る」、「入って来させる」ものを自分が思えば、この「現実社会」に立ち返り、自分もこのなかの一員である、ということのつらさ、と思う。
今自分が関わらないではいられない、このネット、SNSのことを、どうしてもキルケゴールの訴えていたこととなぞらえる。なぞらえないではいられない。
「徳」のことはソクラテスも荘子もよく訴えて(そんなキルケゴールほど痛切にではなく聞こえるが)いたもので、これは人間に備わった、かけがえのない生命にも等しいものだった。
荘子は「ああ、人間の徳も堕ちたものだよ」と嘆いていたが…。
以前、某ブログで感じたことをそのまま書けば、ある人にコメントをしたことがある。よくやりとりもしていたが(こちらの一方的でなく)どうにも申し訳ないが、ずいぶん「偉そう」な、居丈高な、ああ、なんでこんな偉そうなんだろう、と正直感じながら… 自分も偉そうだったのかもしれない、でもコメント、人とのやりとりでは、そんなツノは出したくない、これでもそういう儀礼はわきまえているつもりで、しかしやはり「偉そう」な、妙に自信に満ち溢れた、そんな物言いのコメントをよく頂いていた。
正確なところはわからない、わからないことを書くのも、と思うが、どうもその方は、かなりの「人気ブロガー」であったらしい。いや、フォロワーが何千といたり、いいねも沢山あるようだった。ぼくのブログなど、そんな数は一ケタもいいところで、でも自分としてはそんな数はどうでもいい。だが、どう考えても、それが自分の狭い考えに通ずるのかもしれない、そうだとしても、やはりかれの妙な自信、どこから来るのか、その偉そうな感じ、居丈高な、人を見下げたような感じは、彼の気質だけに依るもの、とは思えなかった。
そう、狭い考えの自分として考えられたのは、「この人のこの自信は、この数、自分はこのブログで多くの人に認められている」ということから来る自信なんじゃないか? そう思ってしまった。ほんとうのことはわからない。
でも、やはりそういう人は多いのではないかと思う。自分の存在意義、存在価値が、フォロワーの数、もらう「いいね」の数で、自分でそう決めて、そこから来る「自信」だったんじゃないか? 僻みではなく、そう考えてしまった。いや、性格ももちろんあるだろうが、どうみても、よくわからない「自信」、ふわふわした、足が地に着いていない、根がその人の中にないような「自信」、偉そうさ、に感じられて… もっとも自信や偉そうさは、そんなものかもしれないが、それにしても、どうにも違和感が感じられてならなかった。
もしかして、多くの人がそうなのではないか?
だからフォロワーを、いいねを、いっぱい増やしたいのではないか?
いや、これは情けない、嘆かわしい、笑いたくなるくだらなさだ。ところが、どうもこれが「価値」あるものであるらしい。少なくとも、その人にとっては。そしてそういう人が、どうも多いらしい。何という馬鹿らしさか…
徳どころの話じゃない、《本質を見ようとしない者は盲目である》、《何を他者に依存しているのか》… 漱石や、いにしえの賢者の石を持ち出すにも当たらない、ひどい「自己価値」、基準があったもんだ。
むなしくないんだろうか。
そりゃ書く作業なんてむなしいものだ、でも価値、自分の自信、自分がしっかり立てる土台、それはこんな「数」に頼るものではないのでは?
そこに依存して、自分を立たせている人は、このネットが不通になったら、できなくなったら、倒れてしまうよ。「過去の栄光」にすがって、なおかつ「自信」を持とうとするのかな。
これを書いたら「人気」がなくなる、とか、自分のイメージが壊れてしまう、とか、自縄自縛、どこまでも「他者依存」を脱けず、書きたいことも書けず、自己欺瞞、自分に嘘をつき他人にばかりイイ顔を見せ(ただ自己満足したいだけのために!)、ずっとそのまま行くつもりなのかな。
信じられない社会なんて、こっから始まってるようなもんだ…