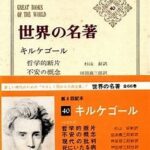ところで、キルケゴールの生きた時代にももちろん戦争があった。「わが著作活動の視点」は1848年に書かれたと推定されるらしいが、この年、デンマークはプロシアと戦い、敗戦したという。(しかし俗なこと、俗であることの最も大きな社会、世界的影響が戦争ではないか? 常にどこかで戦火が起こり、それはいつもいつも、いつもなのだ)
空気を吐くように人は戦争をする。そこには「人と比べること」… 人と比べることによって自分で自分を不幸にする、不幸と思う… 心理の働きがあることは、「野の百合、空の鳥」で感動的に描かれている。
そのままでも十分幸せに暮らせたはずの鳥が、ほかの鳥より勝ろう、ホレあの鳥たちはお前よりこんなに幸福なのだぞと他の鳥にそそのかされ、それまでの生活をうっちゃり、「あの幸せそうな鳥のようになろう」としたことから不幸になったことが童話のように描かれている。
「野の百合」は植物としての宿命である「そこから動けない」百合が、誰にも見られず、誰にも気づかれなくても、そこに咲いている百合を「思い煩う人間」が見ることで多くのことを学ぶという、やはり教話的な物語が美しい文体で描かれている。
感動的であり美しいのは、読んだ自分がそう感じるからだ。
まだ自分はキルケゴールが戦争について書いている文に出逢っていないが、このように美しい、美的な感動体で描かれているもの(それは自分がそう感じるのであって、美的で感動的であるのがどういうことかは自分にはわからない)には、それだけで十分すごるほどの平和さ、やすらぎ、歓喜がある。
この感動、昂ぶりは、あの戦争に向かう兵士、遠隔操作で爆撃をする「自分の手を汚さず、血に染まらずに相手を殺める者の気分の高揚にも通ずるものなのか、とも思うが、同じ精神の高揚にしても、この精神が戦争を起こすのだとしても、美しいものには悲惨な血の争いはない。その痕跡があるとしたら書き手の創作のうちの時間だろう、それでも書いた本人はそれによって勲章を得たり名声を得たりしない、そんな下心は持ち合わせていない… ようにみえる。実際、「野の百合」を書いたキルケゴールは、それより限りある自分の生命、その限りまでせっせと創作することにまさに生命を淡々と燃やしたろう。
何も戦争について書くことだけが、反戦の訴えとか、運動である、ということでもない、とは思う。真摯であること、真摯であることでさえあれば、それはおそらく自然平和を思うことに繋がるだろうし、欺瞞、嘘のあるところに逆のものが生じるんだろうと思う。もちろん自分に対しての嘘であり欺瞞であり、また真摯であるということもそうであり、それを書くということでそれが発露される、ということだ。
昨日、一昨日か、やっと「弁証法」なるものの理解ができたと思う。「世界の名著」版のキルケゴールで、「死に至る病」の中にその小さな解説があるのを見つけた。これは助かった。
「絶望は病であり、薬である、と説かれているように、互いに矛盾することが、ひとつのものについて同時に言われること」とあった!
いやほんとにこの中央公論社の世界の名著シリーズは親切で、このシリーズこそ「名本」のかたまり、集合と思う。調べたい語句や人物があれば巻末にあいうえお順に索引があるし、わかりにくい言葉の注釈はその言葉のある文章中のページにある。いちいち注釈のページに飛ばなくてもいい。ほんとに読者のことを考えて、よくつくってくれたと思う!