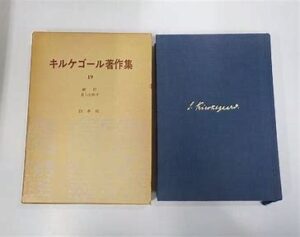キルケゴール著作集… (1)の「あれか、これか」からでなく、気になったものから読んでいる。この「瞬間」は(19)。
セリーヌを読んでいて、いきなりなぜかキルケゴールの「反復」を読まなくちゃ、読みたい!と思い(全く無根拠だった)、その「反復」がとても面白く、著作集のぜんぶを購入し、「おそれとおののき」を読み── 今は「瞬間」。
一度ザッと読み、今はじっくり読んでいる。やはりキルケゴールは何回か読み返してやっとわかるんだなと思う。最初読んだ時はげんなりして、わかるどころの騒ぎでなかったが、二度目になると目が馴染むのかすんなり入って来て読める。
面白いと思う。キルケゴールが発行した機関誌「瞬間」(といってもキルケゴール本人しか書いていないが)。セリーヌが著した「虫けらどもをひねりつぶせ」のような「パンフレット」── 英語以外のヨーロッパの言語には、社会的な主張のための冊子という意味がある(weblio辞書)というもので、キルケゴールはここでかなり強いキリスト教会への攻撃、批判に終始している。
じっくり読み始めてまだ半分にも満たないが、この調子で最後まで行くのだと思われる。この「瞬間」を最後に彼は亡くなったのではなかったか。
彼は、キリスト教を批判していたのではない。キリスト教会、キリスト教界・とさえ書いている、牧師をはじめとするキリスト教、「国家とキリスト教」(手塚治虫は「国家と宗教が結びつく危険性を漫画に描いていた)、「ほんとうのキリスト者をキリスト教会は抹殺している」という意味のことを、延々と書いているように思われる。
たった二、三滴の水を頭に垂らすだけで「キリスト者」になってしまうこと、産まれた時から本人の意思に関わらずキリスト者になってしまうこと、ほんとうのキリスト教とは何かも考えずに無自己のままキリスト者になってしまうこと、そうさせている国家、要するに社会、キリスト教圏内の世界に対して、かなり強めの批判を繰り返し書いている。
これは確かにキルケゴールにとって命がけの批判、攻撃で、そしてそうせざるを得なかった彼の「ほんとう」、「ほんとう」というものに僕はやはり他人事と思えない、共感というのも薄っぺらい、彼の生命、存在、キルケゴールのキルケゴールたる、キルケゴールゆえの「ほんとう」に、全身を持って行かれる、同化するようなものを感じる。
彼は、やはりほんとうのことをいっていたと思う。
自分はキリスト教には疎いので(どっちかというと宗教といえば宗教になり得ようがないブッダの哲学的な「教え」、言葉が好きだ)、そのせいだけではないがキルケゴールのいう「ほんとうのキリスト者」を「ほんとうの人間」と頭の中で変換しながら読んでいる。
キルケゴールはほんとうにそういう「ほんとう」を、ほんとうに訴えたかったのだと思う。
すると、この「瞬間」も実に面白く、実際面白い… と書くのも軽薄だ、何しろキルケゴールは当時のキリスト教会のボス的存在、監督者に向かって、しかもその人とキルケゴールは知己どうし、彼が幼い頃から「世話」になった人だ、に向かって攻撃を加えているようなものなのだから。
もちろんキルケゴールは人類的なもの、的どころか人類を、人間を、その人間を見る自己をよく省察して、そこからあれだけの著作を重ねたのだろうから(レギーネに対しても!)、偉い立場にある人や、自分をバカにする往来の子どもや大人も、「人間のひとり」にすぎなかったとしても、やはりそうとうな勇気が要ったろうと思わざるをえない。
要る要らないの範疇でない── やはりそれは違う、間違っている、しかも決定的に重要な、人間としてそれは大切な、大切な問題なんだということについては、書かざるをえなかった、言わざるをえなかった、「攻撃」… 批判する以外なかった。
攻撃でも批判でもないとしても、そうなってしまう。
しかしこう書いていても、キルケゴール、彼のことをおもうと、何か胸に来る。
彼はほんとうのことを云っていた。
この「瞬間」のどこだったか… 「内面性」という日本語に「ほんとう」というルビがふられていたと思う。また、「個人」と「人格」という言葉に、自分は強い意味を感じた。
ほんとう、というものは内面性の中にしかあり得ず、また、人格というものも、個人のなかにしかあり得ない。
「個人(人格)」、「内面性(ほんとう)」。
どうにも、引っ掛かる、ほんとうのことをいっている言葉に思う。